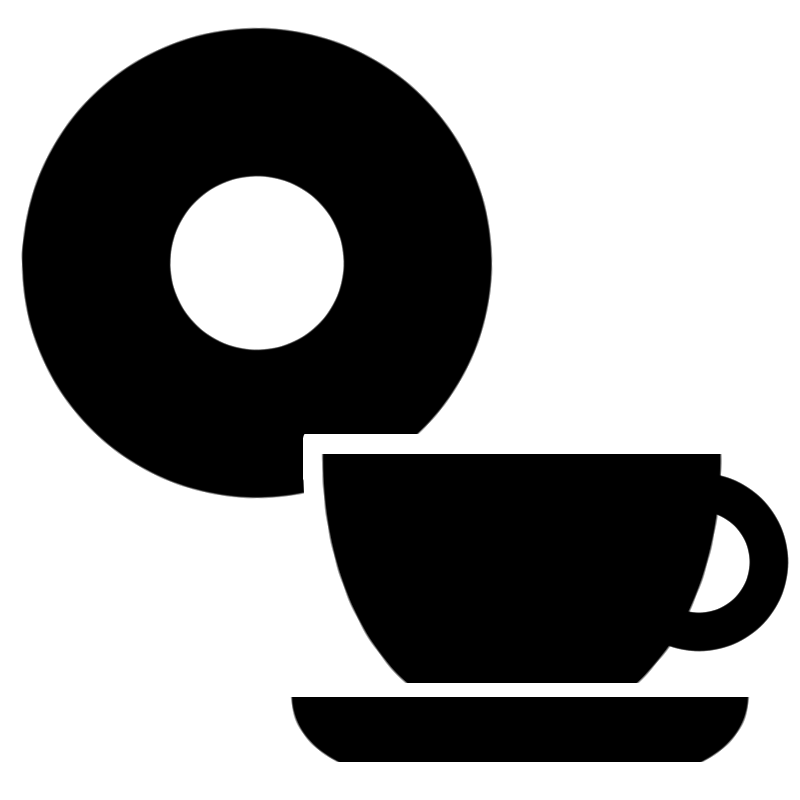ミジと宵の主な役目は『瘴気の谷』の調査であった。
“エキスパート”と呼ばれる数少ない調査団ハンターの中でも彼らは殊更特異な二人組で、本来であればハンターと編纂者がペアになって行動するところをハンター同士で行動している。つまり、一期団のフィールドマスターと同じく、ハンターでありながら“狩猟”と“編纂”が同時にできるのだ。
とはいうものの、編纂は宵が務めることが殆どである。操虫棍を扱う彼女は虫を始めとした動植物への造詣が深く、新大陸の生態系に対する好奇心も旺盛だ。これまで見聞きし、体験した事柄と新大陸での発見を照らし合わせては日々の発見に感動している。
対する双剣使いのミジは身軽で隠密行動に長けており、装衣を活用することで大型モンスターの巣にも容易に入り込むことができる。ギルオスやオドガロン、ディノバルド亜種など一癖も二癖もあるモンスターはもちろん、果てはヴァルハザクの寝床にまで忍び込めてしまう。
ミジが見たものについて宵が丁寧にインタビューして言語化したハンターノートは、仲間のハンターたちの間でも重宝されている。
一緒に過ごす時間が長くなるにつれ、二人の仲は深まっていった。
「長時間の調査活動を可能にするために」と瘴気に曝されても耐えられる装備を作ってみたが、結局は調査活動の名目でなるべく長く共に過ごしたいだけなのは、彼らの周りの人間なら皆知っている。まあ調査拠点の各所によくある公然の秘密だ。
仰向けに倒れたミジが見上げた目線の先には、倒れている自身を興味深そうに見つめる宵がいた。 彼女がしゃがんだときにギルオスコイルのスリットから素足の太ももがのぞく。
「ミジくん」
黒基調の防具や昼間でも常に陰鬱で薄暗い瘴気の谷に不似合いなほど白い肌が印象的だった。
「大丈夫ですか?」
心配そうに、でも心なしか微笑んでいるようにも見える宵に大丈夫と返そうと思っても、先ほどギルオスから浴びせられた麻痺毒のしびれが取れず、満足にうなずくこともできなかった。 麻痺は解毒薬や漢方薬で治るものでもないし、ウチケシの実は麻痺状態では咀嚼も難しい。つまり、時間経過で良くなるのを待つしかないのだ。
加えて、今日は大型モンスターの調査活動で隠密行動をする予定だったため、お互いのオトモアイルーは部屋で留守番をさせている。たたき起こしてくれる相棒がいない。宵がミジをたたき起こすこともできるが、なぜか彼女はそれをしない。
「た、す……け……」
「このあたりには肉食性の虫はいないから大丈夫。もし現れても追い払いますからね」
ちがう、とミジは言いたかった。たかってくる虫は不愉快だが、今すぐこの痺れを解いてほしい。分からないふりをしているのか、本当にわからないのか、ジッと宵の目を見つめても、彼女は微笑むばかりだ。
オオシナトモミジが宵の腕を離れてあちこち行ったり来たりしている。なんとか目で追うと、集まってきたカンタロスやスカベンチュラを追い払っているらしい。
このままでは本当に大型モンスターが来て二人とも危険だと思ったミジは、痺れが薄くなってきた右腕をついて無理やり身体を起こした。ふらふらと倒れそうになる身体を宵が支える。
「……ぁ、ぅ」
「無理しなくてもいいのに」
だが、ミジが立ち上がったことで何か諦めがついたのか、彼を支えながら宵は近くのキャンプに向かった。
テントで手当を受け、ようやく落ち着いたころにミジは「なんですぐ起こしてくれなかったの」と尋ねると、宵はこともなげにに「だってミジくんが可愛かったから」と言った。
「宵ちゃんって、ちょっと変」
そう思ったが、彼女の嬉しそうな笑顔はやぶさかではないので、ミジは何も言わないことにした。