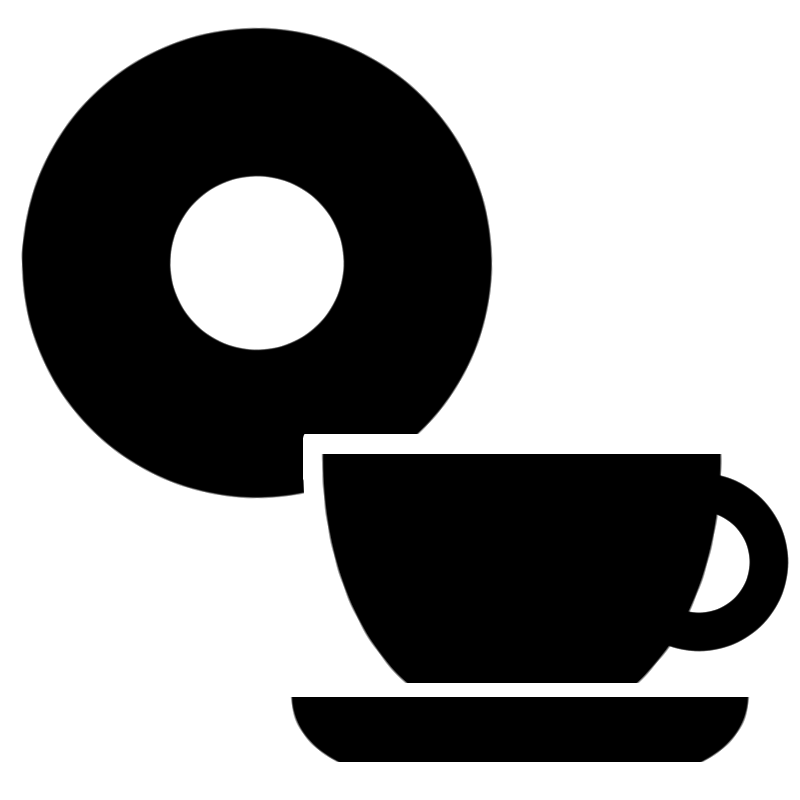Wehrwolfが本拠地にしている屋敷の敷地内には、小さなオペラハウスがある。組織のボスであるファーテルの故郷であるドイツのベルリン国立歌劇場をモデルにした建物だ。クラシックスタイルを好むファーテルのために、外観は戦前の劇場に似せてあり、収容人数は五十人にも満たない、本当に小さな劇場だった。
他に観客もいない中、最前列の中央の椅子にはヴィンツェンツとフリーゼ腰かけていた。目の前には小さなテーブルが置かれており、その上には二つの独特な形のグラスと、水が入った一本のボトルが用意されている。
既に、ポンタルリエグラスの球体部分には、ペリドットのように鮮やかな透きとおった緑の液体が注がれていて、グラスの上部に橋を架けるように先が尖ったスプーンがかけられている。その上には角砂糖も乗せられていた。
二人のグラスに注がれているのは『アブサン』。複数のハーブを配合した薬草系リキュールの一種であり、かつてその中に含まれるニガヨモギの向精神作用が幾人もの人間を破滅へと導いた、と云われている。
勿論、現在は成分の含有量を調整することによって合法的に製造されているが、ドイツにて製造・流通・販売が解禁される1981年までは、Wehrwolfは密造アブサンによって莫大な利益を得ており、この酒はいわば組織の恩人ともいえる『緑の妖精』なのである。
照明で照らされたステージには、頭上で手を組んで歯をガチガチと鳴らす男が一人と、それを取り囲むように銃を構えるヴィンツェンツの部下が三人。
「まるで、スプーンの上の砂糖みたいやなぁ」
頬杖をついたフリーゼが愉快そうに目を細めた。
脚を組んだヴィンツェンツは表情を変えることなく、舞台上で既に泣きそうになっている男に問いかける。
「お前、何故ここに呼び出されたか、わかる?心当たりがあるだろう」
男は震えながら首を振った。
その様子に、ヴィンツェンツは眉を顰め、ため息をつきながら「フリーゼ」と呼びかけた。
頷いたフリーゼはタブレットを操作し、舞台装置の音響を鳴らす。スピーカーから流れてきたのは、男が売人と口裏を合わせ、売り上げを横領している最中の会話だった。
「あかんやろ、こんな雑な仕事しとったら」
自らの裏切りの証拠が大音量で流れる中、ついに泣き出した男は膝をつき、ヴィンツェンツに向かって祈るように叫んだ。
「た、頼む!許してくれ、フィーア!金は必ず返す!」
フィーア(四番)と呼ばれたヴィンツェンツの眉がピクリと動いた。
「……そうだな、金を返してもらえるなら許す」
ヴィンツェンツは立ち上がり、カツカツと足音を鳴らして舞台のもとまでゆっくり歩み寄る。
その後ろで、フリーゼがスプーンの上の角砂糖に火をつけた。
「ただし、金を返すのはお前じゃない。お前の妻と、娘に返してもらう」
ヴィンツェンツの許す、という言葉に一瞬安堵の表情を浮かべた男だったが、妻と娘の名前を出された瞬間に涙は引っ込み、代わりに脂汗がどっと噴き出した。
フリーゼは、スプーンの上でぷつぷつと音を立て泡立ち始めた砂糖に、ボトルの中の水を慎重に垂らし始めた。透きとおった緑に混ざった水に非水溶成分が析出し、グラスの中身は乳白色に白濁していく。
「妻と娘だけは……」
「それから、お前のことは許すけど、組織に裏切り者はいらない」
土気色の顔をした男が言葉を絞り出す前に、ヴィンツェンツが右手を上げた。
その瞬間、舞台機構が作動し、男は文字通り“奈落へと吸い込まれていった”。銃を持って男を取り囲んでいた部下たちに視線を投げかけると、彼らはそそくさと舞台袖へはけていく。
ヴィンツェンツが席に戻ると、すでに二つのグラスの中身は乳白色に染まり、空席の主に飲み干されるのを今か今かと待っていた。
席に着き、最初と同じように足を組むと、フリーゼがグラスを掲げた。応えるようにヴィンツェンツもアブサンを手に取り、グラス同士を触れ合わせる。
涼やかな音が鳴るのと同時に、劇場には舞台から消えた主役の断末魔が響いた。