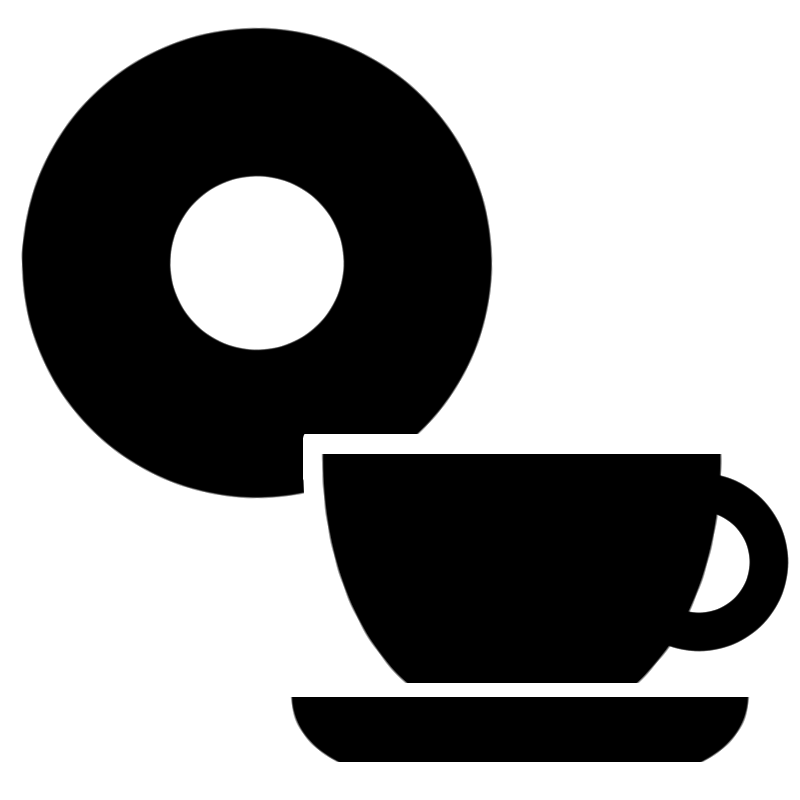前任者が異動になったため、新しい部下を育てることになった。
名前はモーゼス、と言った。
ベビーフェイスではあるが、そこそこ整った顔。最初は声が小さいのとコミュニケーション下手なのが目についたが、私の言ったことは何でもよく吸収して、こなしていった。
人の顔と名前の覚え方。
ある程度の種類の酒、煙草などの嗜好品の楽しみ方。
スーツとネクタイ、革靴の選び方。
テーブルマナー。
シチュエーションごとの振る舞い方。
表情の隠し方と、ご機嫌の取り方。
「ボキャブラリーを増やせ。語彙はあればあるほど良い。馬鹿に合わせるのは簡単だが、頭の良い連中に自分を認めさせるのは一筋縄じゃいかない」
「わ、わかった」
「訛りは消して。人前ではどもらず堂々と喋ること。返答に困るような質問をされて、考える時間が欲しいときは黙ったりせずに、一度相手に聞き返して時間を稼ぎな」
「……わかった」
特筆すべきは彼の観察力と手先の器用さだ。
私が教えるまでワインも飲まないし、葉巻など触ったこともなかったらしいが、一度見せただけでコルクの開け方も、シガーカッターの使い方も覚えた。
「自分が、世間一般の人間よりほんのちょっと詳しいって自信があるジャンルは?」
「クラシック音楽と、ヴァイオリン」
「いいね。お偉いさんはそういう育ちの良さそうな趣味を好むやつが多い。社交の場にもなったりするから、オペラやオーケストラの観劇マナーも覚えておいで」
「うん」
どちらかといえば高尚な方面に分類される趣味を持っていたのは幸運かもしれない。教える手間が省けるから。
そして、いよいよ実戦に沿った教育を始める時がきた。
この仕事で重要なのは人の心に入り込み、必要な情報を得ることだ。
見た目は十分魅力的、黙っていると少しきつそうな印象もあるが、喋ると愛嬌がある。迂闊な人間ならば、このギャップだけで彼に気を許してしまうだろう。
「女を口説いたことは?」
この容姿で年ごろなのだから、一度や二度は火遊びしたこともあるだろうが、“ちゃんとした”口説き方を覚えさせなければならない。とりあえず彼の女性遍歴を確認しようという気持ちで尋ねたが、予想外にも彼の顔はさっと青ざめた。
「……ない」
「ない?別に怒ったり笑ったりしないから、正直に言って」
「本当に、無いんだって」
「……恋人は?」
「今まで一度も」
「片思い」
「ない」
「一夜の過ち」
「それも、無い」
一通り答え終わると、モーゼスは困ったように視線をあちこちにやった。
腕を組んでじっと見つめていると、とうとう観念したようにため息をついた。
「俺、ゲイなんだ」
消え入りそうな声だった。
自分の性質のせいで何度も不快な思いをしたのだろう。知らなかったとはいえ、私も教育中に男の相手は女であることを前提に話を進めていたので、その点は反省しなければならない。
「……男が好きなの?」
「うん……」
「奇遇だね。私も男が好き」
モーゼスが目を見開いた。
「ベルって冗談言えたんだな、ははは……」
「重要なのは、あんたが仕事で女を抱けるかどうか。それから、好きでもない男を抱いたり、抱かれたりするのに耐えられるかってこと」
「……」
厳しいことを言っているの百も承知だった。しかし、性差を利用した仕事は嫌になるほどある。できない、というのならば、他の人材を探すしかない。
ここでお別れ、か。
モーゼスは、私の目を見て、にこりと微笑んだ。
*
*
*
「ワインのリストをお持ちいたしました」
「リストは結構よ。今夜の料理に相応しいものを選んでいただけるかしら。ああ、せっかくだから高いものからね」
「かしこまりました」
ウェイターが恭しく頭を下げ、去って言った。
向かいに座るダニエルはワインの値段が心配で気が気ではないようだ。
「……怒ってる?」
彼は俯き気味ながら、ちらりとこちらに視線を向ける。
「ちっとも」
「嘘つくなよ。怒ってるだろ?」
「……どうしてモーゼスを私のところへ?」
ダニエルは少し口の端を上げ、安堵したように「そのことか」と頷いた。
「ベルなら上手に使いこなせると思って」
「そういうことを言っているんじゃない。彼の本質を知っていて、私の下につけようと思ったのは何故?」
「才能あったろ?」
「だからってわざわざ私のやり方じゃなくてもいいだろう」
「それは……おっと」
ソムリエがワインを運んできた。
説明を聞き流しながら、ダニエルの様子を伺う。いつもと変わらず、飄々とした感じだった。
流れるような所作でワインがグラスに注がれ、ソムリエが去っていったのを確認すると、ダニエルは再び言葉を続ける。
「自尊心を保たせるのに必要なのは、忠誠心だ」
「忠誠心?」
「勿論、モーゼスには他の道があった。でも俺はお前と組ませるのが一番良いと思ったよ。絶対お前に懐くから」
「……」
「『どんな凌辱を受けても、信頼できる上司の為なら耐えられる』、『どんな屈辱を受けても、可愛い部下の為なら耐えられる』……その献身は、組織への忠誠に成り代わる」
こういうとき、ダニエルは目を閉じて笑う。
瞳の奥に光が宿っていないのを気取られることを嫌っている。
まんまとダニエルの思い通りに動いているのが納得いかなかった。舌打ちでもしてやりたかったが、それはこの店に相応しくない下品な行為なので、ただ睨みつけるだけの抗議にとどまった。
口当たりの良いワインを楽しめるような会話は、それ以降も起こらなかった。