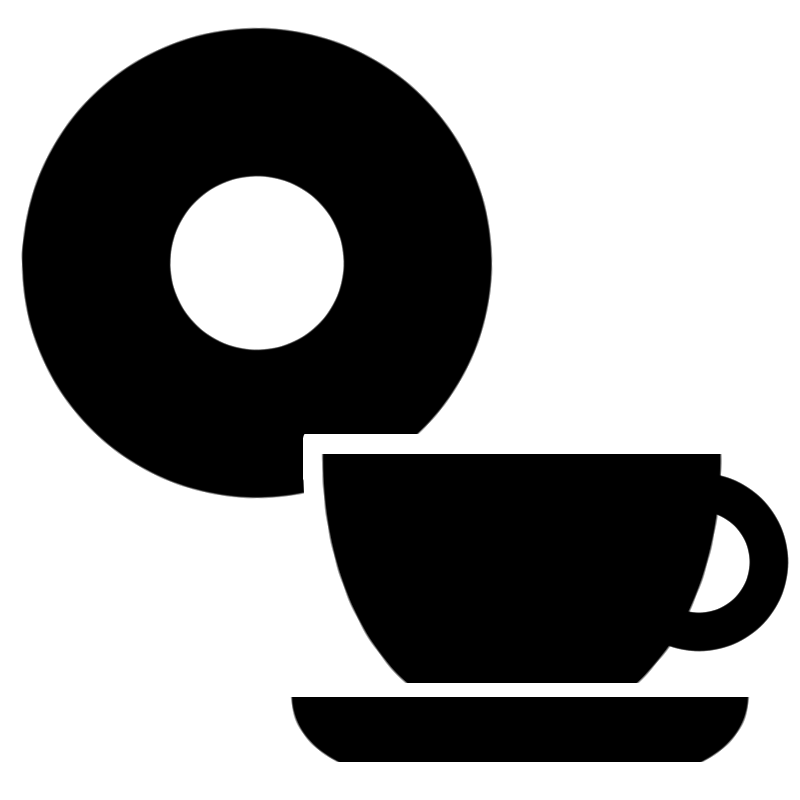- グルメの胃袋は味覚に限らず、あらゆる情報を食い尽くす -
自分が一番最初に起きたかと思ったが、ダイニングに入るとマシューがキッチンに立っているのが見えた。
ダイニングテーブルの上は、チョコレートが皿の上に載っている程度で、昨日の宴会がまるで夢だったかのように片付けられている。昨夜ある程度のところまでは片づけた記憶はあるのだが……、これはもはやマシューが強迫観念で早朝に掃除をこなしたようにも思える。
「おはよう」
「おはよう、サリー」
当の本人はグレープフルーツをしぼり器にかけながら、にこやかに挨拶を返してきた。グレープフルーツの横にスポーツドリンクと蜂蜜。さしずめ、『二日酔い解消カクテル』の制作中とでもいったところか。
「食パン、自分が食べたいだけ切って」
マシューは『二日酔い解消カクテル』の材料の傍ら、パン一斤とナイフが用意されているのを指さした。
「ありがと。あんたは?」
「そんなにいらねぇ。薄めに一枚」
「OK.」
「他の連中は?」
「当分起きないだろうねぇ。もうぐっすり」
「じゃあブランチになるかな」
柔らかなパンにナイフを入れるさなか、開け放たれた窓から朝の冷たい風が入ってくる。さわやかな香りの正体はこの家の周りに生い茂っているミントによるものだろう。
自分とマシューの分の食パンをトースターにセットして電源を入れた。マシューは空のペットボトルに二日酔い解消カクテルを入れ終え、冷蔵庫にしまったたところだ。
「コーヒーメーカーは?」
「こっちの棚の二段目。でも豆が無い」
「じゃあホットミルクでいいか」
「うん」
壁にかけられたフライパンや鍋は綺麗に手入れされているが使い込まれたあとがある。無論、備え付けの調味料も使いかけ……。
トースターが鳴った。香ばしい匂いが食欲をそそる。皿にトーストを出して、レンジで温めたミルクを自分と彼の前に置く。ダイニングテーブルの席につかず、キッチンで食事をするというのはつまみ食いのようで背徳的だ。
カリッとしたトーストの表面に木苺のジャムを塗りながら、「ここは何なんだろうねぇ」とマシューに尋ねてみた。彼は「さあ」と言うだけだった。
しばらくサク、サクという咀嚼音だけがキッチンに響いた。
「アンタは昨日からずっとキッチン使ってたから分かってると思うけど、ここは人の生活感がありすぎる」
「皿の枚数からして四人家族かな」
口の端についたパンくずを指で拭いながら、まるでなんでもないことのようにマシューが答える。
「どう思う?」
「気にしたって仕方ねぇだろ。ダニエルが言うには”バカンス”なんだから」
「まあねぇ、おっしゃるとおりだけど」
リーダーを信用していないわけではないが、“ドイツの片田舎で数日を過ごすバカンス”と言うのが自分の中でどこかひっかかっていた。
しかし、考え事をすべき脳は、たった今口にしたトーストを消化するために、血液を胃に回し始めている。
「レオンにコーヒー豆も買ってきてもらおう」
「ああ、それがいい」
私たちはミントの香りに包まれるキッチンで、しばしホットミルクを堪能した。