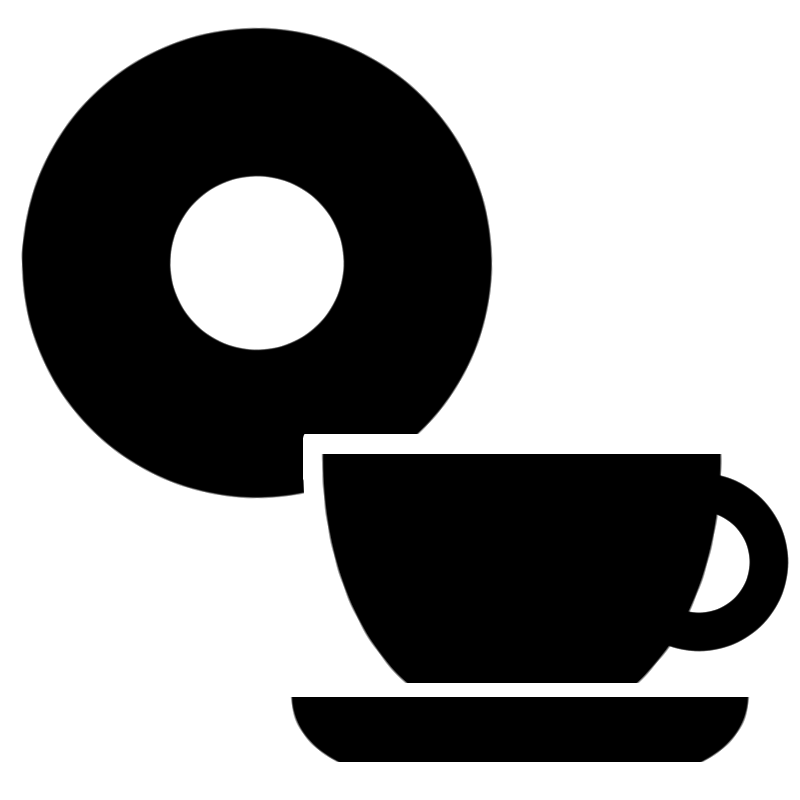– 嘘はつかない。隠し事はしない。ただ“何も言わない”ってだけ –
ベネットが空のジョッキにビールを注ぎにいったその一瞬、リビングが俺とダニエルの2人きりになった瞬間を見逃すはずがなかった。
「地下、あるんだよな」
そう問えば、ダニエルは一瞬目を見開いた後、いたずらっ子のような笑顔を見せた。
「さすが。歩いただけでわかるもん?」
「まあね」
本当はただの勘で、ダニエルにはカマをかけただけだった。もしも違ったなら適当に別の話をするだけだった。
「“この家の地下”には何があんの?」
「さぁな、実は俺もまだ見てねぇんだわ。階段は見つけたけど」
「俺って信用ねーのな」
「隠してない。マジだって。なんなら後で一緒に見てみる?」
「後でって……」
今じゃねえのかと言いかけたとき、ベネットとジャグ、そして煙草から戻ったベルが同時にリビングに入ってきた。
「なんだよー!こっちのテーブル全然なくなってないじゃん!」
有り余る料理に対して、ジャグが目を輝かせる。チョコレートの包み紙を剥いて一粒、自分の口に放り投げた。あまりに美味そうに頬張るもんだから、俺もつられてチョコレートを手に取る。
ちょうどそのとき、モーゼスも煙草から戻ってきた。こいつはこいつでうわの空、といった感じだ。ベルと何を話したかは知らないが、何かしら考えることが出てきたのだろう。
口の中に、チョコレートの中のラム酒の甘い香りがじんわり広がった。
席を立って、家の中を少し探ることにした。
先発組が多少の掃除をしたからか、それともこの家を管理しているドイツ人が綺麗好きで元々清潔だったのか。『まったく埃っぽくない』。たとえ、ここがバカンス用の貸家だったとしても、つい最近まで人間が生活した痕跡が残りすぎている。
リビングから出た廊下、突き当たりには二階へと続く階段。その真正面に、鍵のついた扉。
「トイレなら、リビングから出てすぐだぜ」
振り向くとダニエルが立っていた。
首から下げた革ひものネックレスの先には、小さな鍵がぶら下がっている。
「そこは後にしとけ」
「……ちゃんと声かけろよな」
ダニエルの横をすり抜けて、用を足すためにトイレに入った。