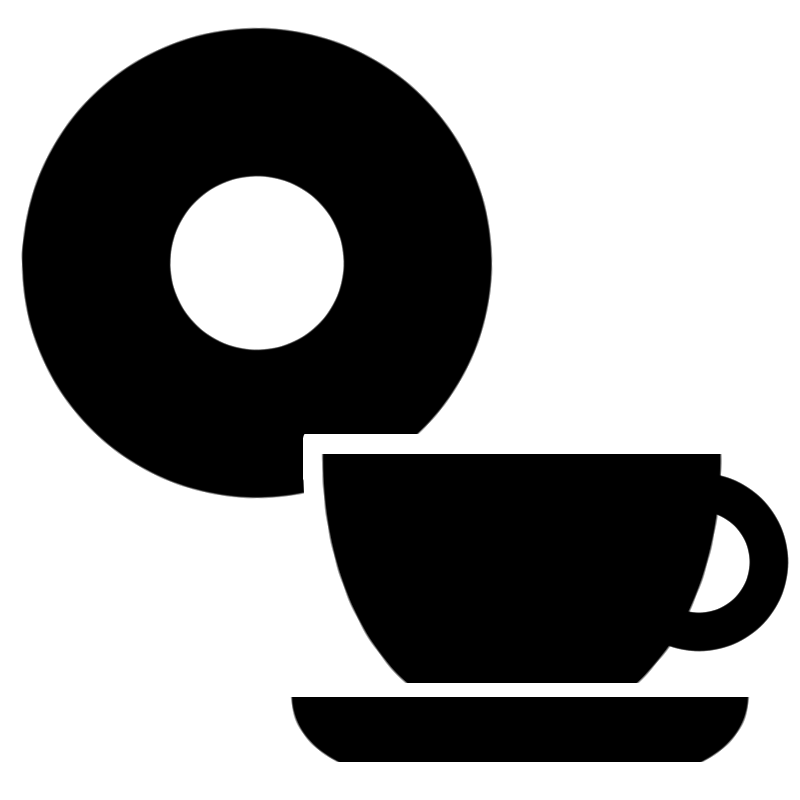– 美味しいことは良いことだ –
昨晩から降り続く雨は、今朝も同じくらいの弱さで街を濡らしていた。
じめじめとして気温が上がりきらない中、街へと下る車の中はクーラーのおかげで少し肌寒いくらいだ。
「チーズにハムにサラミ、ザワークラウトはまだ半分くらい残ってるから……」
助手席のジャグがリマインダーを指折り確認する。
「晴れてたら手分けしたけど、傘も無いし皆で固まって動いた方が良さそうだな」
「ああ、そうだねぇ」
会話が途切れる。
カーラジオから流れる落ち着いたカントリーミュージックと、打ち付ける雨の音が何とも言えない寂しさを醸し出していた。
昨日、ジョンが怪我をしてからというもの、この2人はいつもより口数が少ない。マシューが釣果で作ったフォレレ・ブラウ(ドイツの魚料理:マスのスープ煮)も、一晩で無くなることはなく、今日の昼にようやくなくなりそうと言った具合だ。
「明日には雨も上がるって話だけど、今日いっぱいは降るみたいだね」
「マジかよ。洗濯もんどうすんの?」
「乾燥機あったけど、あれ動くのかなぁ?」
生乾きで臭くなったらやだなぁ、とジャグが唇を尖らせる。
===
片田舎に大きなマーケットは無く、個人商店を回って食糧を調達した。
ハーブの練り込まれたヴァイスヴルスト(白いソーセージ)、スパイスの効いたサラミ、クラッカーに付ける用のクワルク(フレッシュチーズ)、大きな塊のベーコン、あと野菜と卵、柔らかくパンのようなプレッツェル。
痛みそうなものはクーラーボックスにしまって、菓子類の調達をすることにした。
「あっ、そういえばバウムクーヘン食べてなくね!?」
多くの食べ物を目にして、やっと本来のテンションを取り戻してきたのか、ジャグが目を輝かせながら通り沿いのバウムクーヘン専門店を指差す。
「寄ってみるか」
と、マイカが店の扉を開けた。
甘い香りに包まれる。
店の棚には糖衣でコーティングされたものや、チョコレートでコーティングされたもの、切り分けられたや丸ごと売られているもの、様々なバウムクーヘンがあった。
気の良さそうな店主と、その奥さんと思わしき女性が「いらっしゃい!」と迎え入れてくれた。
「うわぁ!どれにしよう〜!」
ジャグは早速、カウンターのガラスケースに張り付かんばかりの勢いでバウムクーヘンの品定めを始めた。
横目でマイカを見やると、あまり楽しそうではないようだ。
「……アンタはまだ元気出ないんだ」
「え?……ああ、」
「昨日のこと、気にしてんの?」
「うん、まぁ……」
「もうよしなさいよ。ジェーンは何ともなかったし、ジョンも怪我したけど普通だったんでしょ?」
「ジョンは……そうだけど、今朝までジェーンと喋ってないんだ。タイミング掴めなくて」
「……」
たしかに、ジェーンは昨日から殆どジョンに付きっきりで、今日の買い出しにも参加してない。
1人で話していたのに反応がなく、怪訝に思ったジャグがこちらを振り返って手招きした。
「2人もこっち来てよ。一緒に選ぼう。いくつ買う?」
「丸ごとのやつ2つってとこかな。ジャグ、お前が選んでいいぜ」
「……」
一緒に選ぼうと言ったのに断られたことに気を悪くしたのか、ジャグは眉をひそめる。だが、一瞬で表情を作り直し、店主の方に向き直った。
「とびっきり美味しいやつが欲しい!2つ!」
「とびっきり美味しいやつ……?」
「そおー!こいつ友達と喧嘩しちゃったんだけどさ、一緒に食べて仲直りできそうなやつ!」
店主が目を丸くしているところに、ジャグがマイカを指差す。マイカが「おい、ジャグ!」と慌てて肩を掴むが、カウンターの奥の女性が「まあ」と笑った。
「うちの人もね、仲直りのときはバウムクーヘンを焼くのよ」
「お、おい、お前、お客さんの前だぞ」
「いいじゃない。友達と仲直りできるといいわね。私のオススメはこれ」
奥さんはホワイトチョコレートが薄く塗られ、コーティングされたバウムクーヘンを指差した。店主も、やや恥ずかしそうな感じでいた。
「ううん……」
「貴方、いつも焼いているやつでいいじゃありませんか」
「そ、そうか。私がいつも焼くのは……」
指差したのは、プレーンのシンプルなバウムクーヘン。ただ、他の品より一回り分厚い。
「じゃ、それを1つずつ!」
満面の笑みで注文するジャグに、奥さんも、店主も、私も、マイカも、皆つられて笑った。
丁寧に品物を包んでくれた2人が、店の入り口まで見送ってくれた。店主はマイカの目をまっすぐ見つめる。
「下手でもいいから、自分の気持ちを伝えたらいいんだぞ」
「ど、どうも」
「ちなみに、俺のバウムクーヘンはこのへんで一番美味いからな、謝るときに成功する確率は……」
「確率は……?」
神妙な顔の店主に、マイカは思わず息をのむ。
「十割だ!」
パッと明るくなる周囲に、また笑いが起こった。
「知ってた!だって美味しいものは無敵だもんね!2人ともありがとう!」
ジャグの言葉に、店主は親指を立てて答えた。
車にバウムクーヘンを積み込み、私たちもそれぞれ座席に座る。車内はあの店内と同じように、甘い香りで包まれた。次は、ラム酒のチョコレートを買いに。
今日の皆は、なんだか上手くいきそうな気がした。