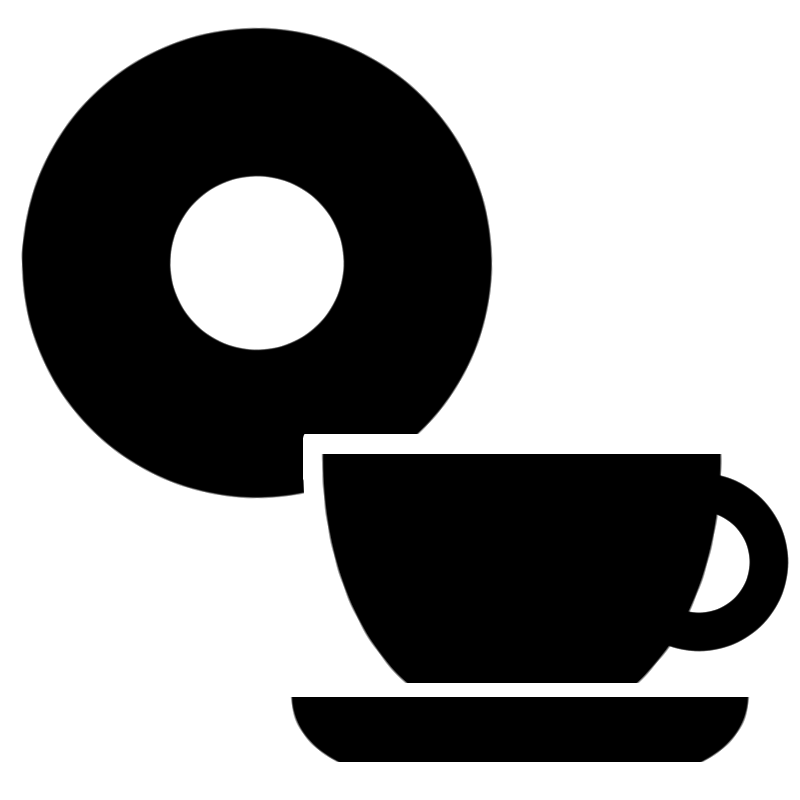– 殺しのライセンスを持っているだけで007になれるわけではない –
乾燥機が動かなかったので、アルファ部隊にリクエストした部屋干し用洗剤が届くのを大人しく待つことにした。午前中、手持ち無沙汰になってしまったので、2階のソファーベッドをソファーの形に起こし、もたれかかる。
1階リビングでは、ベネットとジョンとジェーンがババ抜きに興じている。ベネットは顔に出まくるジェーンが面白くてたまらないらしい。
「お前は皆と遊ばないの?」
女性陣の荷物部屋から、着替えとメイクを済ませたベルが出てきた。そして、そのままソファーに腰掛ける。
「ベルこそ、皆のところに行かねぇのかよ」
切れ長の瞳に捉えられる。
ベルは家を空けているのがほとんどで、気まぐれに呼び出されたとき以外は、あまり会うことはない。
思えば、ここに来てからというもの、こんなに近くにいるのに触れることすらしていない。
「そんな風に言うなら、行こうかな」
と、立ち上がろうとしたベルの腕を掴んで、引き寄せた。
俺に肩を抱かれる形になっても、いつも通りのポーカーフェイス。
そのまま、彼女の頭を抱え込むようにキスをした。
舌で唇を割り開けば、ためらいがちに迎え入れられる。口の中は、苦い煙草の味。絡められた舌を吸い上げれば、一瞬肩を震わせる。唇を離されてしまわないように、頭に回した腕はそのまま。塗ったばかりのグロスが移るのも構わずに、下唇を食むと、隙間から熱い吐息が漏れた。
たまらずに、行き場を失くしていた手を胸にかける。揉みしだくように力を込めた瞬間、とうとう肩を押されて、唇が離れた。
「よせ、シャツが皺になるだろう」
ベルは息を弾ませながらシャツを整える。
ここで止めるのかよ。シャツが皺にならなきゃいいのか?じゃあ脱がせるか?という言葉が頭の中を駆け巡ったが、階段を昇る音が聞こえて来たので、俺は慌てて移ったグロスを袖で拭った。
「結局一回も勝てなかったじゃねぇか」
「コンセントレイション(神経衰弱)なら負けないもん……」
ベネットにおちょくられるジェーンの頭を撫でながら、ジョンはリビングの扉を開けた。
俺もベルも普通に座って話していたようにしていたが、ジョンだけが目ざとく俺の袖についたグロスを見つけ、目を細めた。
「ベル、ブラックジャックとかポーカーでベネットのことコテンパンにしてよ」
ベルは、膝にすがりつくジェーンの頭を優しく撫でた。
「トランプはもう飽きたなぁ」
ベルの標的にされたくないベネットが、一生懸命目をそらしている。
それを見たベルはふっと笑った。
「じゃあ宝探しでもするかい?」
「宝探しって?」
ジョンが首を傾げると、ベルはスキニーのポケットから一本の鍵を取り出した。
「それどこの鍵?」
「そこの部屋」
リビングの隣、鍵がかかり初日から開かずの間だった部屋の鍵だと言う。
「ダニエルからは、元々荷物部屋にあった物を移動させて押し込んだって聞いてるけど、まだ開けてないんだよね」
「っていうか入っていいのかよ!」
この場にいる全員が面食らっていた。
ベルはさっと立ち上がり、扉に向かう。ベネット、ジョン、ジェーンに続いて、俺も立ち上がって、鍵を開けるベルの後ろ姿を見つめる。
鍵が外れた扉はスムーズに開いた。それと同時に、少し埃が舞い上がる。
部屋はリビングと同じほどの広さで、奥に二段ベッド、そしてダブルサイズのベッド、大きな鏡のついたドレッサーが鎮座している。ただ、ベッドの上にはシーツやマットレスが無く、本で出来たタワーや何かを詰め込んだ箱が積まれていた。ブラウン管のテレビや、箱形のパソコンなども置いてある。
入り口からまっすぐのところに、ストレージへの扉があった。ベネットが率先してそれを開けると、洋服ダンスが2つ並び、さらにその向かいに本棚があるのが見えた。
「おお、DVDとかあるじゃん」
ジョンがベッドの上の箱を覗き込むと、そこにはDVDやVHSが詰まっていた。「あとで皆で観よう」と、DVDを選別しはじめた。
ジェーンはその隣で積み上がっている本を一冊ずつ確認している。
「あ、これ知ってる。蛾の標本壊しちゃうやつ」
ドイツの著名な作家の短編集を手に取ったジェーンは、嬉しそうにジョンに話しかけた。ジョンもどれどれ、とそれを覗き込む。
俺はストレージの本棚の方に行った。
「こっちは英語ばっかだな」
表の部屋の本はドイツ文学やドイツ語の本ばかりだったが、ストレージはうってかわって英語の本ばかりだった。不思議の国へ迷い込む少女の話や、守銭奴の老人がクリスマスに3人の幽霊と出会い改心する話、二重人格の男が奇妙な事件を巻き起こす話……
とりあえず、俺は暇つぶしのための一冊に、世界一有名であろうスパイ小説の第一作目を手に取った。
洋服ダンスの引き出しを開けたベルが、一瞬だけ目の色を変えたのを横目にみながら。