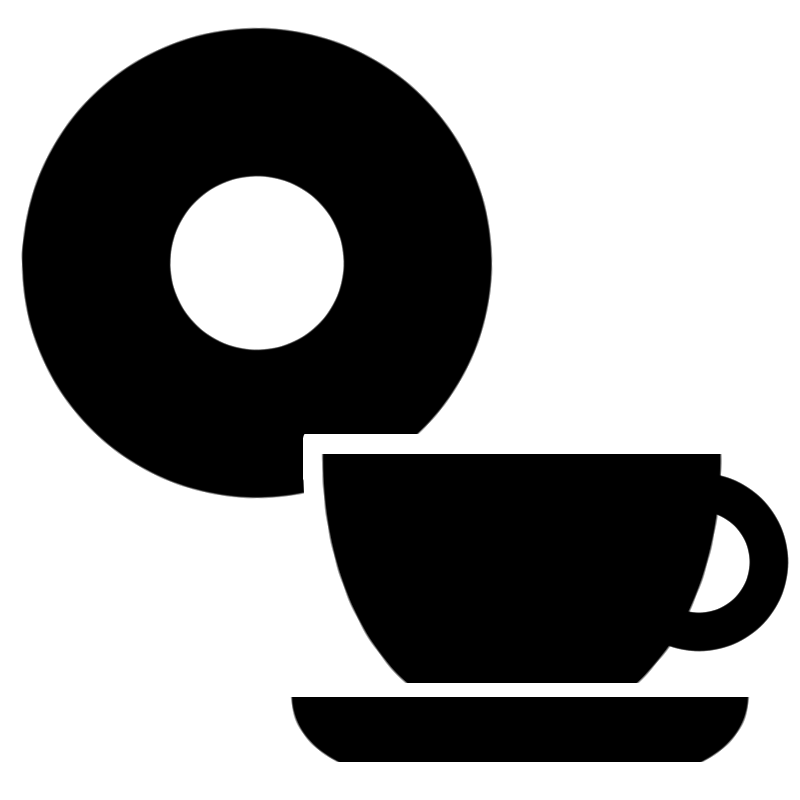– やっていることは、いつだって誰だって変わらない –
最終日の酒宴に備えて、皆が早々に休んだ。
時刻は午前2時過ぎ。1階、リビングのソファで横になっていたモーゼスの肩を静かに叩き、地下室へと続く扉を開いた。遅れてモーゼスがやってくる。ダニエルは既に作業中らしく、暗室からカチャカチャと物音がする。
「よぉ。2人ともきたな」
ダニエルは昨日現像したネガを、印画紙に照射していた。それらはまだ現像液には漬けられておらず、バットの横に積み重ねられている。
「俺は露光していくから、2人で仕上げていってくれ」
「わかった」
ダニエルの言葉に頷き、モーゼスが現像液の前に立つ。
昨日に引き続き、四角く切り取られた像が姿を現していく。
街中を闊歩する兵士。小銃を持つ兵士。小さな戦車。現れていく写真はすべて、物陰から撮られたものと思わしかった。
「盗撮、だよな……スパイだったのか」
モーゼスがぼそっと呟いた。私もダニエルもそれには答えず、淡々と作業が進められていく。
「ここから、ベルが見つけたフィルム。『1945』」
「1945……」
「ケースにそう刻んであった」
受け取ったモーゼスが、液の中で印画紙をゆする。
「何これ、真っ白……、……」
ダニエルの手によって現像液に浸された2枚目の印画紙は、燃え盛る街の様子を映し出した。
逃げ惑う人々。
置き去りにされた乳母車。
倒れる兵士。
燃えている、すべてが。
「ブラウンフェルスは」
現像液の中に次々と現れる、モノクロでありながら生々しい破壊の様相に魅入られたモーゼスを現実に引き戻すように、ダニエルが口を開いた。
「疎開者や被爆者の人々で溢れかえった。この写真を撮ったやつも、それに紛れてここに来たんだろう」
空襲から明けた街の写真。
物のように積み上げられた死体、道に乱雑に転がされた死体、焼け焦げてなお寄添う死体、崩れ落ちた建物。
水の張られたバットに、それらが次々沈められてゆく。
「ここからは、俺がカメラを見つけたときに入ってたフィルム」
おずおずと揺らした枠の中に現れたのは、
庭いじりをしている、見知らぬ女性。
リビングのソファでキルトを縫う女性。
小さな男の子と、絵本を読み聞かせる女性。
泥だらけで戯れる、2人の男の子。
皆一様に笑顔だった。恐らく、このカメラの主の家族となった人々だろう。
やがて、白く四角い印画紙に、見慣れた人物たちが現れはじめた。
リビングでくつろぐジャレッドとサリー、キッチンの入り口に立つダニエル、マッシャーを持ったマシューの怪訝そうな顔、リビングのテレビ台、放置された酒瓶、2階のソファーベッド、肩を組むマイカとベネット、ジョンに寄り掛かってうたた寝するジェーン、煙草を吸うライオネルと、その奥でピンボケした私。
水ですすいだ写真たちを乾かすため、壁に張られたヒモにクリップで吊るしていく。
鼻をすする音がした。
振り返ると、モーゼスが泣いていた。
「……結局、無かったな。このカメラの、持ち主の写真」
彼は涙を雑に拭って、つとめて冷静な声で呟いた。
「戦後の混乱期、所在や出自の分からない難民がわんさかいた。撮影者のスパイも、“そのときに死んだ”のかもしれないな」
震えている声を咎めることなく、ダニエルが答える。
吊り下げられた仲間たちの笑顔と、積み上げられた死体のコントラストが、『1945』の非現実感を浮き彫りにしていった。