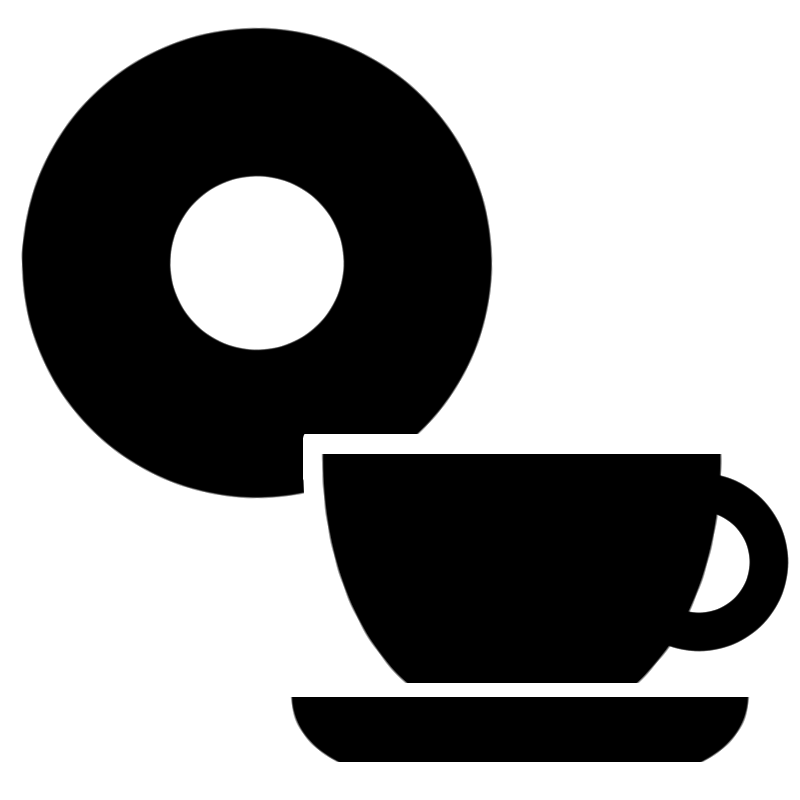– Epilogue.2 : 彼だけが知っていた –
最終日の時間が過ぎるのは、驚くほど早かった。
モーゼスがベルとリビングのソファで一緒に眠っていた理由を問い詰めたら、「休暇明けに早速仕事に同行してもらうため、打ち合わせをしていた」と、それらしい理由をつけて庇われた。そう言われてしまえば、こちらからは何も言えず納得するしかなかった。
宴の後を片付け、快晴となった空の太陽がてっぺんにたどり着く前に、荷物をまとめて皆車に乗り込む。
「じゃあ、俺とモーゼスとベルは、この家の鍵返さないといけねえから、お前らとは別の飛行機で帰るわ」
「……分かった。気を付けろよな」
「そんじゃ、引率よろしくな。家に帰るまでがバカンスだぜ!」
肩を叩かれる。
俺が乗ってきた車にはサリーとジャグを、マイカが運転するワゴンにはジェーンとジョン、ベネットは往路と同じく助手席にマシューを乗せ、それぞれ空港へと向かった。
「See you around “Braunfels”.」
===
──……夕暮れ。
ガソリンの匂い。
そこらじゅうに生えていたミントの爽やかな香りは、すっかり人工的な匂いで塗りつぶされていた。
「“連中”に連絡は?」
ガソリンの入っていたタンクを適当に放りながら、ベルが尋ねる。
「した。待機してるってよ。派手にやろうぜ」
車を移動させたモーゼスが俺たちに歩み寄る。
そして、ポケットからライターを取り出そうとして、ベルに止められた。
「ライターくらい自分のがある」
胸ポケットから取り出されたシンプルなジッポーは、火が付いたまま、ガソリンの撒かれた家に投げ込まれた。
夕暮れの太陽と同じくらい鮮やかなオレンジが、たちまち家を包む。
70年前のあの日、ドレスデンを焼いた炎もこんな色だったんだろうか。
すべてが燃えていく。
皆で過ごしたリビング、
ダイスとルールブック、
ソファーベッド、
中身の少ない救急箱、
キッチンのマッシャーやケーキナイフ、
魚を入れたバケツ、
ラインガウとフェーダーヴァイザーの空き瓶、
トランプとビアグラス、
物置部屋のDVDやVHS、
英語の蔵書や洋服ダンス、
ジェームス&パーディの散弾銃、
ピクニックバスケット、
その中に隠された白い粉、
写真を現像した地下の暗室への扉、
ライカIIIaとフィルム『1945』、
家族の写真と仲間の写真、
暗室の床下に埋めた老人の死体……
まるで、この一週間ここで過ごした日々など無かったかのように。
「帰ろう」
ベルが助手席に乗り込み、モーゼスも後部座席に座った。俺も運転席に座り、往路とは違う裏手の道を通って山を下りた。
ドイツの片田舎、山の中で起きた派手な“ぼや”は、大したニュースになることも無かった。