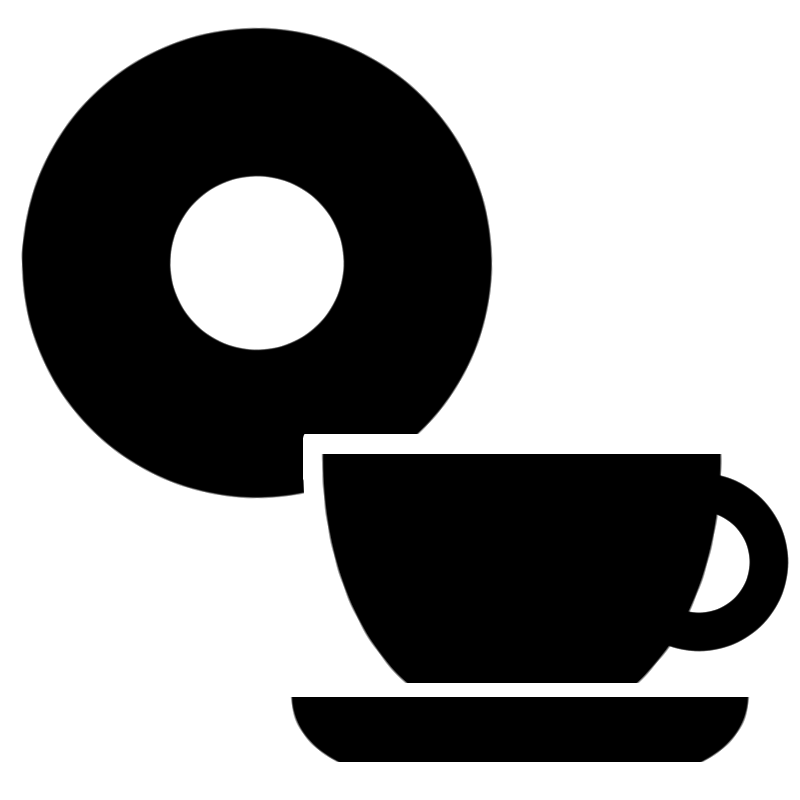– Epilogue.3 : 彼だけが知る –
…
……
…………。
春先のイギリス、某所。
「それでは、そのように事を進めていただけるかしら」
目の前に座っている年若い女性―確か、“シャロン”と名乗った―は、穏やかな笑みをたたえた。
その隣に座る、これまた年若い男性―“エリオット”と呼ばれていた―が、目の前に書類の束を差し出す。
「こちらが、当時のエージェントたちのリストです。コードネームと最初の任地が記されています。何分、数が多いので、時間がかかるかと思いますが……」
書類を受け取る一挙一動まで、シャロンとエリオット、そしてその両脇に立つ2人の男性の鋭い視線が絡まる。
慣れないスーツに身を包んで、ただでさえ息苦しいのにこの雰囲気。反吐が出そうになる。
「正直なところ、どれくらいで見つかりそう?」
「……3か月ってとこかな。処分に関しては、準備期間が欲しい。実行は“バカンス”の時期にでも」
「構わないわ。こちらでも協力できそうなことがあったら、いつでも言ってちょうだい」
「人道に反する罪を犯さない程度に?」
軽口をたたけば、シャロンの傍らに立っている金髪の男性が睨みを利かせる。
「口を謹んでもらおうか。君たちの代わりなどいくらでもいるんだぞ」
つまり、俺達のチームはトカゲのしっぽであり、不都合があればいつでも切り離されるということだ。精鋭ぞろいの組織とはいえ、さすがに国家相手では分が悪い。今回ばかりは、ヘマをすれば簡単に見捨てられるだろう。
「しかし、国外での騒ぎに関して、本当にアンタらがもみ消したりすることが可能なのか?」
「もちろん、しかるべき機関に協力はしてもらうつもりよ。でも、全部はかばいきれないかもしれないから、くれぐれも慎重にやってちょうだい」
「70年も前の勝ち負けに、未だに縛られるんだな」
「戦争に負けるってそういうことだわ。正義の権利は勝者にしかないもの」
そう言い放ったそいつの顔が、今までこの世で見てきたどんな物より醜悪なものに見えた。
エリオットの傍らにいたブルネットの男が口を開く。
「70年前のドレスデンで起こったことに、もうこれ以上、新しい発見は無い。たとえ、“エージェントがそこで薬をさばいて資金をイギリスに流していた”としても、証拠が無ければ事実にはなり得ない」
書類を鞄に仕舞い、嫌味なほど上等なソファから腰を上げる。
部屋のドアノブに手をかけ、振り向かないまま尋ねた。
「なあ、もしも俺がその秘密を世界中にバラしたら、アンタたちはどうするんだ?」
返ってきたのはシャロンの声だった。
「世間一般の人々は、貴方《ゴロツキ》の言うことなんてまともに聞かないわよ」
ああ、そう。
そうだな。
それは実に的確な答えだ。
===
約束通り、3か月で生死不明だった1人のエージェントを見つけた。
既にかなり年老いており、名前はドイツ風に変えてあったが、直接接触した際に本人がそれを認めた。妻に先立たれ、息子2人もそれぞれ巣立っていき、彼にはもう怖いものなど無いというのだ。
「いい所だな、ここは」
「そうだろう。バカンスにでも来たらいい」
「……俺はあんたを始末しなきゃならない」
「もう充分生きた」
「依頼主はあんたの祖国だぜ」
「……いいんだ」
「……」
「祖国はあの時、間違いを犯した。私はそれに携わった1人だから、間違いを認めて正すときなんだ。本当はあの日、私は死ぬべきだった」
「……今年のバカンスはここに来るよ、仲間も連れて。その時にまた話そう」
そう言って、老人と別れた。そのとき彼はこんなふうに言い残した。
「私はイギリスを愛している。今は、ドイツも」
===
依頼の内容をベルにだけ伝え、ブラウンフェルスで一週間過ごす計画をし、その日が来た。
だが、先んじてクライアントと共に滞在先に到着したベルから電話があった。
「クライアントがターゲットを始末した。家の中の証拠は全て探し出して処分するようにと」
本当は、老人の最後の思い出に酒でも飲み交わす予定だった。
バカンスの日程は変更せず、最終日のみ計画を変更し、家ごと燃やして抹消するとクライアントに伝えた。
俺とモーゼスが家にたどり着く前に、ベルに老人の遺体を地下に運んでもらい、その遺体を床下に埋めるのはジョンに手伝ってもらった。二晩かかった。
ライカはその時に地下の暗室で見つけたものだ。
===
旅行を終え、任務完了の報告と“滞在の延長を希望”をしたライナスを迎えに行くため、本部に行った。
帰りの車の中、クライアントから暗号化もされていない平文のメールが届いた件について、システム担当であるライナスから追及された。
「びっくりしちゃったよ。だってイギリス政府のドメインからメールが来るんだもん」
終わった任務の話であったが、ライナスには平文のメール一通から概要がすべて筒抜けになってしまったようだ。
本人が言うには、メールが傍受された可能性は低いとのことだが、リテラシーに厳しいライナスの叱責からは逃れられない。
「俺のクライアントのことは、他の奴らには内緒な、内緒」
内緒、などという言葉がこのチーム内にどこまで通用するかは分からないが、箝口令はしかないよりましだ。国を相手にした仕事の話など、当分は振られたくない。
「……俺、ドーナツ食べたくなっちゃったなぁ」
我がチームのエンジニアの口封じは、イギリス政府のエージェントにするそれよりも遥かに安上がりで楽なものだ。
彼のお気に入りのドーナツ店に寄るべく、俺はハンドルを切った。